どうも。まるたろうです。
今回は一級建築士試験対策として過去事例「妙喜庵待庵」についてみていきます。
今回のキーワード:妙喜庵待庵 千利休 草庵茶室
まずは過去問題をどうぞ。答えは最後に。
(1級学科Ⅰ:H27-No2)
妙喜庵待庵(大山崎町)は、16世紀に造立された、利休好みの二畳の草庵茶室である。
妙喜庵待庵(みょうきあんたいあん)は、千利休による設計とされる茶室建築で、現存する最古の茶室として知られています。所在地は京都府大山崎町にあり、日本の茶道文化を象徴する重要文化財です。この建築物は、一級建築士学科試験の過去問題にも登場しており、茶室建築や日本の伝統建築を理解する上で欠かせない事例となっています。
試験との関連性として、意匠設計や伝統建築の特徴を問う問題、文化財の保存に関する知識を問う設問などに出題されることがあります。
まずは場所と外観を把握しましょう。
Googleマップのリンク↑に用意していますので一度見てみましょう!
(※Googleマップの埋め込みを使用しています)
参考情報:文化庁公式ウェブサイト(https://www.bunka.go.jp/)
妙喜庵待庵の詳細
草庵茶室とは
草庵茶室は、簡素でありながら深い精神性を宿した茶室の形式を指します。この形式は、自然との調和を重視し、華美を排した設計が特徴です。妙喜庵待庵は、その代表的な例とされ、以下の特徴があります:
- 簡素さと調和:
- 草庵茶室は、贅沢を排除し、自然素材を活かした作りが特徴です。
- 茶道の精神である”わびさび”が設計全体に反映されています。
- 千利休と草庵茶室:
- 千利休は草庵茶室の普及に寄与し、待庵はその中でも最も完成度の高い事例とされています。
参考情報:茶室建築の研究(建築学会誌)
デザインと特徴
待庵は、わずか二畳台目(約4.5㎡)の小さな空間でありながら、草庵茶室として千利休の”わび”の精神を具現化した設計となっています。草庵茶室とは、簡素で自然との調和を重視した形式の茶室であり、茶道の精神を象徴する重要な建築スタイルです。
- 間取り:
- 茶室は二畳台目という極めてコンパクトな間取りで、入室者に親密な空間体験を与えます。
- にじり口という小さな出入口が設けられており、利用者は身体を屈めて入室します。これは、身分の違いを超えて平等な場を提供する茶道の理念を反映しています。
- 構造と材料:
- 壁は土壁仕上げで、自然素材の持つ質感が特徴的です。
- 天井には竹が用いられ、素朴でありながら趣のある意匠が施されています。
- 建物全体が簡素である一方、床柱や釘隠しなどに細やかな装飾が施されており、茶室特有の美意識が表現されています。
参考情報:千利休の茶室に関する論文(日本建築学会)
歴史
待庵は、安土桃山時代(16世紀末)に建てられたと考えられています。千利休が設計したとされる数少ない現存建築の一つであり、1951年に国宝に指定されました。
出典:国宝・重要文化財データベース(https://kunishitei.bunka.go.jp/)
試験での出題ポイント
例題
- 妙喜庵待庵の設計者とされる人物の名を答えなさい。
- 解答例:千利休
- 茶室建築における”にじり口”の目的を述べなさい。
- 解答例:身分の違いを超えた平等性を表現するため。
関連知識
- 茶室建築の特徴:
- 間取りの制約を活かした空間設計
- 自然素材を活用した建築
- “わびさび”の精神がデザインに反映される
- 文化財保存:
- 国宝に指定されている建築物は、定期的な修復が行われ、原状を維持する努力がされています。
参考資料:茶道文化学会出版物(https://www.sado.or.jp/)
それでは回答です
それでは冒頭の過去問題の答えです。
正しい枝となります。
妙喜庵待庵とか如庵とか孤蓬庵忘筌とか…もうやめて!!!って感じですよね。
試験対策としてはキーワードを頭にしっかり入れて関連付けることが大事になります。
妙喜庵待庵…千利休…室床…二畳…草庵茶室…京都…と何が何なのかはさておき基本的フレーズを頭に入れましょう!寝る前の呪文です!
建築士に役立つ学び
- 空間設計の工夫: 小さな面積を有効に活用するためのデザインアイデア。
- 素材選び: 自然素材の特徴を最大限に活かす方法。
- 歴史的背景の理解: 建築物が持つ文化的背景を学ぶことで、設計に深みを持たせる知識が得られます。
まとめ
妙喜庵待庵は、一級建築士学科試験において重要な事例であり、日本建築の根幹を学ぶ上で欠かせない存在です。この建築物を通して、空間デザインや歴史的背景を理解する力を養うことができます。
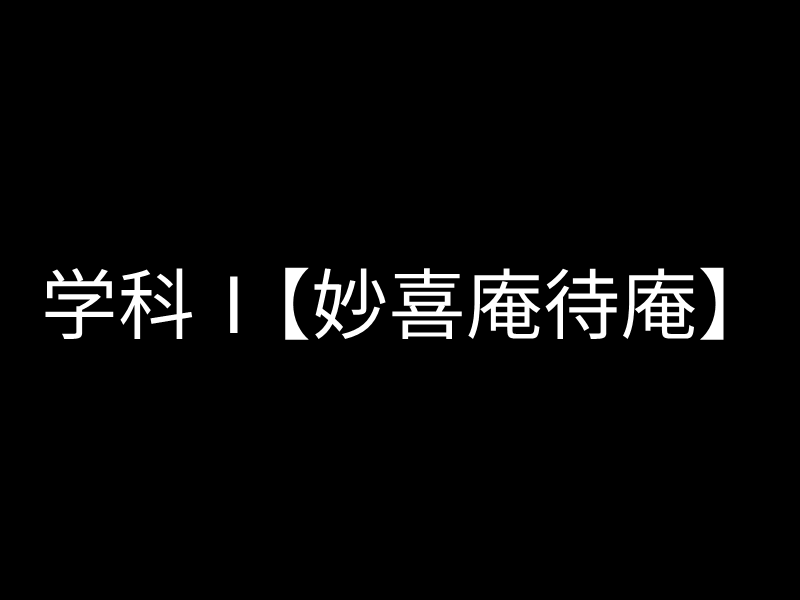
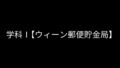
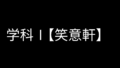
コメント