どうも。まるたろうです。
今回は一級建築士試験対策として過去事例「妙喜庵待庵」についてみていきます。
今回のキーワード:笑意軒 桂離宮 茅葺寄棟屋根 深い土庇 農家風の外観 茶室
まずは過去問題をどうぞ。答えは最後に。
(1級学科Ⅰ:H27-No2)
密庵(京都市)は、17世紀に桂離宮の敷地南端に造立された、茅葺寄棟屋根や深い土庇等の農家風の外観をもつ格式にこだわらない自由な造形の茶室である。
笑意軒(しょういけん)は、京都府京都市の桂離宮内にある茶室です。桂離宮自体は、日本建築の美を象徴する傑作として世界的にも知られていますが、その中でも笑意軒は特に農家風の外観や茶室らしい質素な佇まいで注目されています。
建築士試験では、日本建築史や意匠設計の問題で取り上げられることがあり、その特徴や背景を正確に理解しておくことが重要です。本記事では、笑意軒の建築的特徴や試験対策に役立つポイントを詳しく解説します。
まずは場所と外観を把握しましょう。
Googleマップのリンク↑に用意していますので一度見てみましょう!
(※Googleマップの埋め込みを使用しています)
笑意軒の詳細
デザインと特徴
- 茅葺寄棟屋根 茅葺(かやぶき)の寄棟屋根は、笑意軒の最も目を引く特徴の一つです。この屋根は農家風の外観を強調しつつ、茶室としての静謐さを保っています。茅葺屋根は断熱性や調湿性にも優れており、伝統的な日本建築ならではの機能美を感じられます。
- 深い土庇(どびさし) 笑意軒のもう一つの特徴は、深い土庇です。土庇とは、屋根の延長部分で雨風を防ぐ役割を果たします。深い庇は日差しを遮り、茶室内を快適な環境に保つ工夫でもあります。
- 農家風の外観 茅葺屋根や土庇と相まって、笑意軒は一見すると農家のような素朴な外観を持っています。しかし、内部は洗練された茶室の機能を備えており、この対比が建築的に興味深い点です。
歴史的背景
笑意軒が建てられたのは江戸時代初期とされています。桂離宮全体が皇族の別邸として造営された中で、茶の湯文化を反映した空間として設計されました。茶室という特性上、質素ながらも計算されたデザインが随所に見られます。
試験での出題ポイント
よく出題されるテーマ
- 建築形式
- 茅葺寄棟屋根や深い土庇の具体的な役割と美的価値。
- 茶室建築の特徴。
- 歴史的背景
- 桂離宮の全体構成と笑意軒の位置づけ。
- 江戸時代の建築文化における茶室の役割。
- 意匠設計の観点
- 茶室特有の「侘び寂び」の思想がどのように反映されているか。
- 農家風外観と茶室内部のギャップが生み出す美的効果。
過去問題例
- 「桂離宮内の茶室で、茅葺寄棟屋根と深い土庇を特徴とする建築物の名称を答えなさい。」
- 「笑意軒における茶室建築の特徴を挙げ、その機能的意図を説明しなさい。」
それでは回答です
それでは冒頭の過去問題の答えです。
誤りの枝となります。
密庵ではなく笑意軒ですね。
密庵も笑意軒も同じ京都でしかも茶室です…わかりにくい!!
主な違いとしては建築様式になるかと思います。密庵は書院造を基調とした数寄屋風の造りとなっている点が大きく違います。また別でまとめようと思います。
建築士に役立つ学び
笑意軒から学べる意匠設計のポイント
- 伝統と機能の調和 茶室としての伝統的な要素を備えつつ、農家風の実用的な外観を採用することで、自然環境と建築が一体化しています。
- 素材の選択 茅葺や木材など、自然素材の使用が建築物全体に温かみを与えています。
- 空間構成の工夫 質素な外観と洗練された内部の対比は、現代建築においても応用可能なデザイン手法です。
まとめ
笑意軒は、桂離宮内の茶室として、日本建築の美と機能を見事に体現しています。建築士試験では、茅葺寄棟屋根や深い土庇といった特徴が問われることが多いため、これらの要素を正確に理解することが重要です。
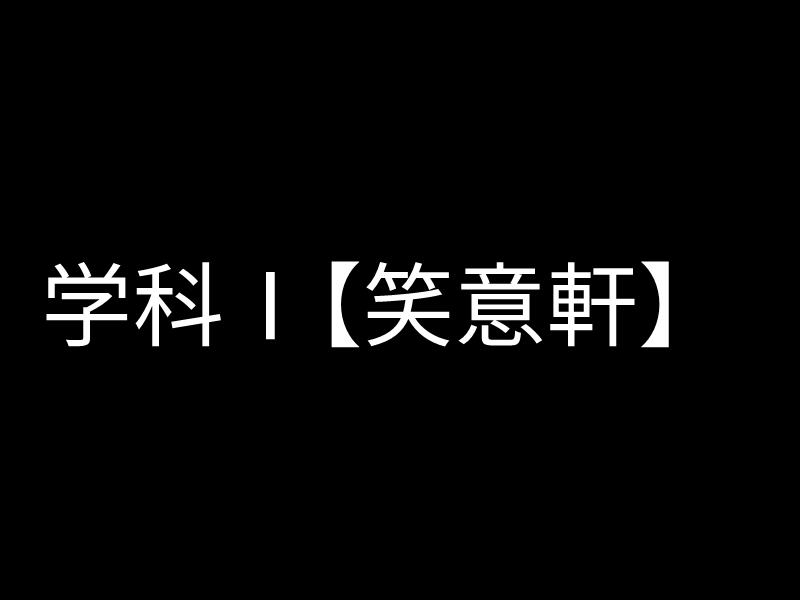
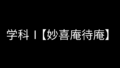
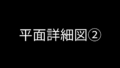
コメント